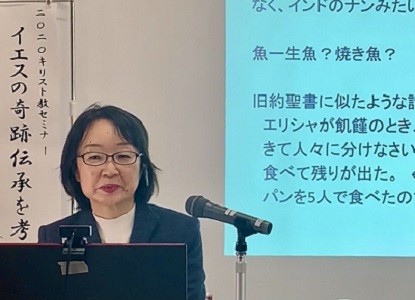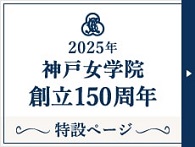第1回 開校前夜の祈り ー少女たちと話合えるようになりたい 2025年7月1日(火)
アメリカンボードによって神戸に派遣された2人の女性宣教師の、出会った
異国の地の少女たちを「魅力的」だと感じ「彼女たちと話し合えるようにな
りたい」、つまり隣人を理解したいという祈りのもと「女学校(おんながっ
こう)」として設立された神戸女学院。今回は学院創立150周年を記念して、
神戸女学院におけるキリスト教理解について、キリスト教と教育制度の発展
の歴史の説明を交えながらお話いただきました。自分のためではなく他者の
ために奉仕できる精神、自身の働きを限定せず異質なものを関係づける力と
いった17世紀にさかのぼる米大陸移住者たちが大切にしていたキリスト教的
人間観に対する思いが、この神戸女学院の教育の中で継承されてきたことに
改めて思いを致しました。先達の祈りは今日も大切にされています。
セミナーの後、大学旧図書館にて開催中の創立150周年記念展示を見学させて
いただきました。

第2回 新キャンパスへの祈り ーBeauty Becomes a College 2026年2月3日(火)
建学(立学)と先達の祈りについて,今回はヴォーリズ建築の岡田山キャンパス
と学院歌”Beauty Becomes a College“にフォーカスしてご講演くださいました。
例えば講堂の講壇上に見られる大アーチに「学舎が教育する」というヴォーリズ
の理念を見ることができます。これは聖書の虹がモチーフで、異質なものを一つ
に繋ぐという意味です。そのために私たちは他者に共感して仕え、自身が神から
与えられた賜物の応答として神の業に参与するのです。
また、エミリー・ホワイト・スミス先生がKCC創設に尽力されてアメリカから
多額の献金が集められ、竹中公務店の第14代店主も土地取得や工事完成に尽力さ
れるなど、見返りを求めずに献げるアガペーの愛が結集されて学舎が完成されま
した。
デフォレスト先生作詞の学院歌にも、神と人の創りしもの、奉仕の愛(原田園子
先生訳)という歌詞があります。私たちは神戸女学院で学んだ者として、意識し
て努力してこれらの先達の祈りを次世代に継承する責任があり、学院創立150周
年の節目にその祈りに立ち帰ることができ感謝です。
-530x400.png)
第1回 旧約時代に見る「愛神」と「愛隣」の思想 2025年2月4日(火)
講師 神戸女学院 院長 飯 謙 氏
学院の永久標語「愛神愛隣」の思想の起源や変遷について、学びました。
「愛神」(申命記6章)と「愛隣」(レビ記19章)は、同じ旧約聖書の中でも、
それぞれ異なる時代に、個別の目的をもつ集団によって編まれた文書に見られます。
講演では、詩編120-134編の「都に上る歌」に注目し、エルサレム神殿へと歩む中で、
来られなかった人のために祈った巡礼者の素朴な言葉が、「愛神」と「愛隣」が
合流するきっかけとなった可能性に言及されました。


第2回 イエスとそれ以降の時代における「愛神愛隣」 2025年2月25日(火)
講師 神戸女学院 大学チャプレン 文学部総合文化学科准教授 大澤 香 氏
「神を愛する(恐れる)」ことと「隣人を愛する」こと。
旧約時代から続くこれらの思想は、イエスが生きた第二神殿時代でも重要な思想でした。
時代による意味や位置づけの変遷を見ると、古代イスラエル人の主であった神が、
民族性を乗り越え普遍的な存在へと変化したことがうかがえる、とのお話でした。
今日の神戸女学院では「愛神愛隣」の精神に基づき、一人ひとりが他者のために
自分が何をなすべきかを考える自主性を養う教育を行っている、と教えていただきました。

第1回 クリスマスオラトリオ
2023年12月12日(火)
6部・全64曲で構成されるこの作品は、降誕節から顕現日までの6日間の礼拝のために、
聖書からの引用を元に約300年前にバッハが作曲しました。
他の曲を転用するなどの工夫を用いて、2週間で書き上げたそうです。
今回は第3部までを、講師が学生時代にコーラスで演奏会に参加したエピソードを交え、
歌声やピアノも用いて解説いただきました。
「賛美歌から多くを学んだ」というキリスト教信者も多くいるが、
教会歴に対応して信仰の養いを目的として礼拝で演奏する「教会音楽」を作り上げたのは
バッハだ、とのお話でした。
*4年ぶりに、対面のみでの開催としました。

第2回 マタイ受難曲 2024年3月5日(火)
2部・68曲から成るバッハの教会音楽を代表するこの作品は、
1727年4月11日の聖金曜日(受難日)礼拝で初演されました。
講師は、バッハのオラトリオや受難曲が、礼拝の形式を想起させる、
⓵福音史家(聖書朗読)、⓶叙唱(聖書解釈)、⓷アリア(奨励)、
⓸コラール(応答の賛美歌)のまとまりを重ねて構成されていることを例と共に示し、
最後65番のアリアが「(自分の心の中に)イエスを葬ろう」とイエスとの一体化を
語っており、ここから「愛神愛隣」や「志の引き継ぎ」の促しを聞き取りたいと
締め括られました。

 第1回 「パウロはどんな人だったのか?」
第1回 「パウロはどんな人だったのか?」
講師 神戸女学院 院長 飯 謙 氏
日時 動画配信2023年2月7日(火)20時~2月20日(月)
第1回キリスト教セミナーは「パウロはどんな人だったのか」と題し、パウロが律法を重んじる厳格なファリサイ派からキリスト教に回心した経緯について、新約聖書のフィリピ、ローマ、ガラテヤ、使徒言行録等から歴史的背景や年代を追いつつ、丁寧に分かり易くご講義いただきました。
パウロはローマの市民権を持つヘレニスト・ユダヤ人、厳格な律法の教育を受けたファリサイ派で、律法の義に関しては非の打ちどころがない者と自負し、教会を迫害する側の人物でした。
しかし、ダマスコでのイエス・キリストとの出会いによって、それまでの全てを損失と見なすほどに回心しました。人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるという信仰義認論を知るに至ったからです。異邦人もすべて神に許されるという教えです。
この教えをパウロが伝道することによって、キリスト教は世界へと広がり始めたとのことです。今回も録画配信での開催となりました。東京など遠方の方々も含め、たくさんの方にセミナーを楽しんでいただくことができました。
第2回 「パウロから見る原始キリスト教」
講師 神戸女学院大学文学部総合文化学科 准教授 大学チャプレン 大澤 香 氏
日時 動画配信2023年2月21日(火)~3月6日(月)
もともとはユダヤ教の分派であったキリスト教が独自の宗教としてのアイデンティティを確立するに至った過程を歴史の流れに沿って、ご講義いただきました。
民族的宗教であるユダヤ教から分岐したキリスト教が、ユダヤ人の二項対立的他者である異邦人をなぜ受容することができたのか。その理由は、古くはアッシリアによる強制移住と、バビロン捕囚からエルサレム崩壊までの第二神殿時代に地中海世界に離散したユダヤ人ディアスポラ(離散の民)の存在が大きかったとのことです。彼らはギリシャ語を公用語とし、ヘレニズム文化の中で暮らし、異邦人に対して寛大でした。その代表的な人物がパウロです。もともとは教会を迫害する保守的ユダヤ教徒でしたが、イエス・キリストとの出会により、ユダヤ教からキリスト教に回心し、律法を重んじることではなく、福音の核心である信仰と恵を説きました。キリスト没後の3回におよぶパウロによる異邦人伝道の過酷な旅についても、地図をたどりながら、詳しくご解説いただきました。
受講者の皆さまから、大変ご好評いただきました。第1回と第2回、違う角度からのご講義でしたので、皆さまには、多面的にパウロの人物像を学んでいただけたことと思います。

2021年度のキリスト教セミナーは感染症対策として、録画配信のみでの開催となりました。
海外や東京など遠方からも受講していただき、皆さまからご好評いただきました。
第1回 聖書の民の捉えた死とその彼方
講師:神戸女学院 院長 飯 謙氏
録画配信:2022年2月1日~2月14日
旧約聖書のテクストをたどりながら、人々が死とその彼方についてどのように捉えていたか、神様から何を示され、どのように信仰 を深められたかをご講義くださいました。
創世記の天地創造の場面の「あなたは塵だから、塵に帰る」という一節は霊肉一元論、死んだら肉体も魂も消滅するという思想を表しているとのことです。古代の人々の死に対する考え方の一例として、遊牧民であるアブラハムの妻サラの葬り方もそっけないものだったというエピソードをお話くださいました。
また、隣接する文化圏からの影響を受け、レファーム(死者の霊)、レファイーム(冥界、陰府と呼ばれる死者の場所)という新たな認識が生まれたこと、神観が変化し、復活の思想や永遠の命といった観念が生まれたことについてもご解説くださいました。
現代に生きる私たちが死を思うとき、隣人愛をもって生きることがいかに大切であるかということ、そして、キリスト教のもつ死のイメージについて「千の風になって」の背景にある死生観を例に挙げて、語ってくださいました。

第2回 現代人の死生観と儀礼
講師:神戸女学院大学 学長・学院チャプレン 中野 敬一氏
録画配信:2022年2月22日~3月7日
超高齢化社会による弔うことの簡素化という現代日本の身近な問題にはじまり、日本人の死生観と儀礼の変遷について、詳しくご講義くださいました。
『古事記』のイサナギ、イザナミの神話や民間信仰の山中他界、常世の国など、死者の国はそんなに遠くなく現世と行き来できる距離だという「お盆」にも通じる考え方が古代日本には、もともとあったとご解説くださいました。また、仏教の葬送儀礼も交え、キリスト教の死生観についてお話くださいました。プロテスタントでは、「死をみて怖がるよりも復活したキリストに目を向け、神の救いと恵みを見なさい。」という考え方であるとのことです。また、仏教もキリスト教もお葬式や法事には、残された者がゆっくりと時間をかけて死を受け入れるという意味もあるとご教示くださいました。
終わりから今を見る「メメント・モリ」の思想や、悲しみの表出、共同体による慰めの大切さといったグリーフケアについてもふれてくださいました。

 撮影風景
撮影風景
今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンライン開催いたしました。ところが残念なことに、第1回はたまたま開始時刻と同時に起こってしまったNTT側の通信障害の影響で、私たちのライブ配信も中止せざるをえなくなり、すでにスタンバイしてくださっていた飯先生、皆さまには残念なことになってしまいました。これを受け、講義の録画のオンデマンド配信に切り替えました。初めてのことで試行錯誤の連続でしたが、ご理解ご協力くださいました皆さまに心より感謝いたします。
第1回 2021年1月26日〜2月28日配信
「奇跡伝承―どのように読まれてきたか」
講師 神戸女学院 院長 飯 謙氏
福音書にある奇跡の物語は、私たちが隣人愛を考える契機になるものが選ばれているのだそうです。物語の超能力的な部分に関心が向かいやすいですが、今までの読まれ方や学問的な解釈などを踏まえて、神が私たちを隣人愛へ導こうとする思いをお話しいただきました。実際にあったかどうかということではなく、聖書のテキストが何を伝えようとしているのかを考える姿勢を大切にすることを改めて教わりました。

第2回 2月9日〜2月28日
「五つのパンと二匹の魚(マルコ6章)―多様な読み」
講師 神戸女学院大学非常勤講師・同志社大学講師
92大96 入 順子 氏
五つのパンと二匹の魚で5千人が満腹になったという「五つのパンと二匹の魚」の奇跡物語(マルコによる福音書6:41~44)ですが、そのまま読むと「こんな話はうそだ」と思う人もたくさんいるでしょう。この物語の多様な解釈について、日常生活のエピソードも交えながらお話しくださいました。
皆がお腹一杯になっただけでなく、12籠いっぱいのパン屑が残ったとあります。パン屑は福音を表し、イエスの祝福がのちの多くの人に伝わるということを表現しているのではないか、と語られました。遠い奇跡の物語ではなく、私たちの身近な出来事でもありうるように感じられました。
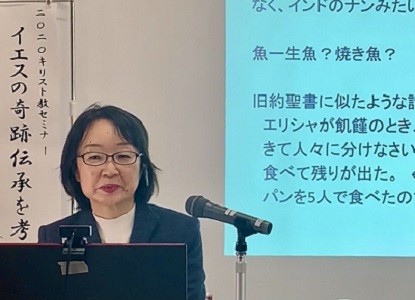
 撮影風景
撮影風景
旧約聖書の「ヨブ記」は、古代ユダヤ人ならだれでも知っている信仰偉人伝「ヨブの物語」と、執筆者によって挿入された「対話篇」で構成されています。この「対話篇」の挿入によって、「ヨブの物語」の背景にある、初期ユダヤ教を支えた応報の教義(神が良い者には恵み、悪い者には災いを下すという図式)の持つ問題点が浮き彫りになっています。
第1回「問題の発端」では、原文のヘブライ語に照らしながら、ヨブの人物像や、1回目の災いに遭った時と2回目とでは、その信仰の応答が微妙に変化していることなど、お話し下さいました。
第2回「友との論争」では、神の義と応報思想の正当性を説き、ヨブに悔い改めを迫る友人たちと、それに反論して自身の義を主張し、不条理の現実を訴え、神の正当性を問うヨブとの議論について、整理しながらお話し下さいました。
第3回「主の創造した世界」は、新型コロナウィルス感染拡大防止のためやむなく中止。それまで沈黙しておられた神ご自身がいよいよ語られるというところでしたのに残念です。


昨年12月に新たに出版された『聖書協会共同訳』の下訳に携われた飯先生に、聖書の翻訳の歴史や訳し方の違いについて、3回にわたってお話しいただきました。
旧約聖書39巻と新約聖書27巻は、キリスト教の正典です。ルターは聖書だけが信仰の規準だとして、1522年に自らドイツ語に翻訳しました。このことが契機となり、聖書はそれぞれの国の言葉に訳されました。
古代は自由に翻訳されていたものが、ルター以降逐語訳・直訳されてきましたが、20世紀半ば以降、意訳される場合もありました。ところが、意訳だと解釈の巾を狭めたり、全体としてのまとまりに欠けたりします。
日本聖書協会の新翻訳では、直訳したものに脚注を加えています。聖書は全体として読むことが大事なので、是非新しい聖書を自ら読んで、さまざまな発見をしてくださいとのお話でした。


-530x400.png)










 撮影風景
撮影風景